|
この記事は2013年秋号です
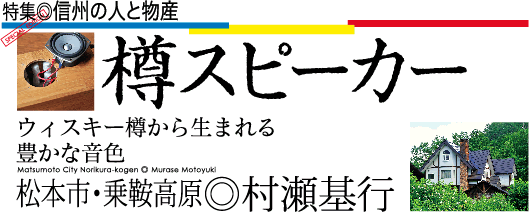 |
|
|
「ウィスキーを熟成する役目を終えた樽材を使ってスピーカーを作っています。樽材は樹齢100年ほどのオークを使っていて、そこから50年ウィスキー樽として使うんです。だから、このスピーカーは、すでに生まれてから150年くらい経っているんですね。そのくらい古い木なんです」
そう話す村瀬基行さんは、松本市乗鞍高原でペンション経営をしながら、スピーカーを制作している。乗鞍高原は中部山岳国立公園内にある自然環境豊かなエリア。約100件の個性豊かな宿があり、一年を通して楽しめるアウトドアフィールドが広がる。
乗鞍高原にある「ペンションウィンズ」。フレンチディナーが評判の宿で、今年でオープンして20年になるという。
村瀬さんは学生時代まで名古屋で過ごし、浜松で商社のサラリーマンとして15年間働いた後に、家族で信州へ移住した。
「スキーが好きで信州へは昔からよく来ていたので、信州しか頭になかったですね」。
スキーのインストラクターや乗鞍岳のガイドをしたり、のりくら観光協会の宣伝部長としても活動している。
「初めてスピーカーを作ったのは高校生のときです。たまたま見つけたスピーカー作りの本を参考に作ってみました。フォーク世代でギターもやっていたので、スピーカーには興味があったんです。
そこからずっと、今に至るまでちょこちょこと作り続けてきました」。
樽材を使ってスピーカーを作りはじめたのは、8年ほど前だという。
「山梨県でペンションをしている知り合いを訪ねた時に、使用済みの樽材が積んであったんです。
何に使うのか聞いてみたら、薪ストーブ用に使っているというので、少しわけてもらったのが始まり。その樽材を使ってスピーカーを作ってみたら、驚くほど音が良かったんです」。
ウィスキーとは麦芽を原料とした蒸留酒。はじめは透明なものが、年月を経てウィスキー樽から染み出る樹液によって琥珀色に変化し、芳醇な香味となる。
「使い終わった樽材は、樹液が抜けているから、抜けた部分に細かな空間ができ、広がりのある乾いた音が出る。この響きがクリアな音になるんです」。
また、通常スピーカーには綿などの吸音材が多く使用されていて、音の1割ほどが吸音材に吸われてしまう。村瀬さんのスピーカーは梱包材の発泡スチロールを吸音材として使用。少量をバランスよく配置することで、よりボリューム感のある、生き生きとした音が再現できる。
ペンション隣にたつ、アメリカ製のキットを組み立てて作ったという小さな工房。ここで村瀬さんは、スピーカー作りに没頭する。
「カンナで削ったり、作業をしているとウィスキーの匂いが、ふわ〜っと香る。樽材には3%くらいウィスキーが残っているんです。樽材のチップを使って、ソーセージやベーコンの燻製もしてるんですよ。お客さんにとっても好評です」。
ペンションウィンズは、音楽好きのお客さんも多い。樽スピーカーを真空管アンプに繋げて音楽を流している。真空管というのは、かつてはオーディオなどに使われていたもので、現代スピーカーはトランジスタ(半導体)が主流。
「真空管アンプでに繋げて聴くと、かすかな響きまで聴こえてコンサートホールのような臨場感を味わえます」。
希少な樽材を使った、広がりのある豊かな音色。
「音がクリアでうるさくないから、何曲聴いていても疲れないです。雨の日なんかに、ここで音楽を聴いていると、とても幻想的な気分になります」。
音楽をもっと聴きたくなる。知っている曲が、新鮮に聴こえる。音楽を楽しみたい人のためのとっておきのサウンドがここにある。 |
|

オリジナル樽スピーカー『Winds Electric』。完全受注生産。小さなものは20cmほどの大きさで4万円〜。 |


少量の吸音材をバランスよく配置することで、音の削れが減り、音が分厚くなるという。 |


村瀬さんオリジナルの『iホーン』(9,500円)。iPhoneやiPodなどを差してどこでも音楽を楽しめる。こちらはベイマツを使用。 |
|
|

紅葉に染まる一の瀬園地(松本市・乗鞍高原)
|
標高3,026mの最高峰、剣ヶ峰をはじめ23もの峰が連なる乗鞍岳。剣ヶ峰山頂は、乗鞍エコーライン(マイカー規制)の終点畳平から歩いて約1時間半と、短めの時間で標高3,000m級の登山が楽しめると人気の山岳スポット(気軽に挑戦しやすいが、3,000m級の高山なので装備は万全に)。9月下旬から10月上旬頃は特に乗鞍エコーラインから眺める紅葉が絶景。ハイマツやナナカマド、ダケカンバのコントラストが素晴らしく、多くの写真家が訪れる。この乗鞍岳の東山麓に広がる乗鞍高原は、原生林や池、個性的な滝など癒しのスポットが点在する高原。ここ乗鞍高原にあるペンションウィンズのオーナー村瀬基行さんは、ペンション経営のかたわら、スピーカーを制作している。 |
|
|
|